なぜ、子どもは本嫌いになるのでしょう?

文字がたくさん書いてあるのが本

読むのはたいへん、つかれる、おもしろくない
というのが、多くの子が一番初めに本に対して思うことではないでしょうか。
どんなに親が

本を読むと楽しいよ!

わからないことも知ることができるよ!
と教えたところで、本に対するイメージはそう簡単には変わらないんですよね。
子どもが「本を読むことは楽しい」と感じることができれば、わからないことは本を読んで自分で学ぶこともできますよね。
そうすると親もラクになります。
なるべく小さいうちに

本っておもしろいなぁ

もっと読んでみたい
と思えるようにしてあげることが大切なんですよね。
親が子どもに本の楽しさを教えてあげやすいのは小学校低学年ぐらいまでです。
それ以降は、子どもが自分のタイミングで好きになるまでは親が介入するのは難しくなります。
それまでに子どもが「本好き」になるように親子で楽しみながら過ごせたらいいですね。
今回は
『本嫌いな子が小学校低学年までに「本好き」になる具体的な方法』
をお伝えしますね。
本が嫌いな子が本を嫌う理由とは
子どもがなぜ本が嫌いなのでしょう?
本を嫌う理由は
からなんですね。
たとえば
・文章を読んでもイメージが湧かない
・文字や言葉がわからないからおもしろくない
・時間がかかりそうで他の楽しいことがしたい
このようなことですよね。
うちの子も初めは文字が多めの本には苦手意識を持っていました。
また、小学校へ行くまではとくに文字を書かせることはしてこなかったので、文字には慣れてはいませんでした。
ただ、小さい頃からずっと寝る前に私が読み聞かせはしていたんです。
図書館などに行けば、興味のある絵本は自分で選らんで借りていたので、子どもはひらがな、カタカナの絵本は何とか自分で読めるようになっていました。
就学前の文字を読み書きすることは

小学生になってからでも遅くないよね
と思いあまり気にしていなかったんです。
しかし、もうすぐ小学校へ入学という頃に、だんだんと不安になってきました。
小学生になるとどの教科でも教科書を読むようになりますよね。
子どもからすると

文字を見るのは学校だけで、おなかいっぱい
そんな気分なのでしょう。
それから、小学生以降になって読む本はだんだんと文字が多い本になっていきます。
そのせいで本嫌いになっても困ると思ったんです。
小学校へ入学する頃からは、どうやってもっと本に興味を持たせればよいものかと、いろいろ考えながらやってきました。
楽しみながら「本が好き」になるための方法
子どもが楽しみながら本を好きになるためには
・自分で本を選ぶ
・物語の世界を音読で楽しむ
・新鮮な世界を知る
・悩みやわからないことを解決してくれる
・読みやすい大きめの文字とたのしい絵
・興味のある話
このようなポイントをおさえていきましょう。
自分で本を選ぶのは、最終的に手にするときのことです。
目の前に置かれている本の中からしか子どもは選べませんから、興味のない本ばかりですと「本はつまらないものだ」と思うかも知れません。
ですから、子どもが興味を持って読めそうな本を揃えるようにしましょう。
子どもの興味がありそうな本がたくさん置いてある図書館や本屋へ定期的に行くのもおすすめです。
気に入った本は購入し、リビングなど子どもがいつもいる場所へ置くようにしましょうね。
それでは、ここから
・本が嫌いな子も楽しめる本はどんなものなのか?
を見ていきましょう。
本屋と図書館へ定期的に連れていく
「本は何のために読むのか?」
それがわからないから、本屋も図書館も好きじゃないのかも知れませんよね。
このことは説明するより体験させた方が話が早いです。
小さい子どもでも小学生、中学生でも同じように
初めはそれでいいのです。
時間管理も家庭学習もそうなんですけれど、その家のルールとして習慣をつけていくのが一番子どもの身につきやすいんです。
小さければ小さいうちの方が、子どもも素直に受け入れてくれます。
初めにどうしても嫌がったら、ちょっとしたご褒美をあげてもよいと思いますよ。
うちの子なら、アイスとかお菓子とかで喜んでました。
それはあくまでも初めのうちだけで、だんだんと1時間ぐらい本のある場所にいることを続けていると、興味がなくても本を手に取るようになるんですよね。
図書館によっては、手塚治虫さんや藤子不二雄さんのマンガも置いてありますので、それいうものでもよしとします。
1、2週間に1回の頻度で30分~1時間ぐらい、いるようにするのが効果的です。
そして図書館に行ったときには、できるだけ本を借りて帰りましょう。
借りる本は、マンガは借りたければ1冊まで、あとの本は子どもが好きな本を選ばせます。(絵本でもOK)
興味がありそうなジャンルの本を選んで見せる
本屋や図書館へ行ったときに、基本は子どもに好きに選ばせます。
すると子どもは、毎回、同じような本ばかりを手に取っていることにい気づくと思います。
それはそれでよいのですが、少し親が子どもの視野を広げるお手伝いをしてみましょう。
今までの会話で子どもが口にしていたキーワードはありませんか?
・気になっていそうなこと
・悩んでいそうなこと
・疑問に思っていること
このようなことを思い浮かべて見てみましょう。
ただし、しつこく言うのはやめましょう。
サラッと軽い感じで、言って見てくださいね。
決して「読みなさい」とは言いません。
声をかけるとすれば
「この本とか、ロクが好きそうじゃない?」
「この前、○○のこと言ってなかったっけ、こんなのあるよ、どう?」
こんな感じがよいのではないでしょうか。
こちらがプレッシャーをかけないように、このように言っても子どもは警戒します。
一度、言ったら、少し自由にさせて様子を見るのがおすすめです。
どんな本に興味を持っているのか?
遠くから子どもを観察して見てみましょうね。
お気に入りの本を選ばせて買ってあげる

図書館に行けば十分じゃない?
そう思いますか?
いえいえ、本屋には本屋に行く意味があるんです。
本屋へ行く【理由1】図書館にはない本が置いてあるから
新刊や話題の本が図書館にはない場合があります。
本屋へ行けば子どもが試読することもできるので、本当に気に入った本であれば購入します。
本屋へ行く【理由2】雑誌や知育玩具、文具など子どもが興味があるものがあるから
子ども用の雑誌は付録がたくさんついていますよね。
小学生のうちは、どんな付録でも興味があるようなんですよね。
親にすれば、手に取って欲しくない?!(けっこういいお値段しますよね)気もしますが「これからもたくさん本を読もうね~」と約束しつつ、たまには買ってあげます。
見本で置いてある知育玩具は、子どもがけっこうハマって頭を使って楽しめるものもありますし「家に置いてあってもいいかも」なんてものにも出会えるかも知れません。
そう印象づけられることが、子どもが本を好きになるための第一歩になるんですよね。
本屋へ行く【理由3】気に入った本は、くり返しいつでも読めるように買うため
本屋へ行く最大の目的は、これです!
毎回、何冊も買うことはできませんが、子どもの洋服をたくさん買うよりは本を購入することにしています。
本はある意味、投資だと思っています。
子どものことに限らず、私自身の本も同じです。
今は電子書籍もありますが、たくさんの本から好きな本を選ぶにしても、子どもがパッと手に取りやすいのは従来通りの紙の本のような気がしています。
家の目につくところに置いてあれば、ちょっとした空き時間にもくり返し手軽に読むことができますものね。
あと手に持った感触とか、私が個人的にも好きなんですよね。
読み聞かせをする
読み聞かせは毎晩、寝る前にしていて、子どもが赤ちゃんの頃からずっと続けています。
もうすぐ中学生になろうとしている上の子、私、小学生の下の子で川の字に布団で横になって本を読みます。
「本を読まない子も好きなる本選び!小学校低学年向けのおすすめの本14選」の記事にも書きましたが、今では私が感情を込めて読むのが楽しくなってしまって、やめられなくなってしまいました。
子どもたちも今だに楽しみにしてくれているようなので、まだまだ続けていくつもりです。
まとめ
本嫌いな子に「どうやったら本は楽しいということがわかってもらえるのか?」を第一に考えてみました。
「本は楽しいもの」
この感覚を小学校低学年までに親子で共感できるようになるといいですね。
そのためには毎週のように本がたくさん置いてある場所に親子で通ってください。
たくさん本に触れあうことで楽しさがわかり当たり前の存在になっていくんですよね。
小学生になるまでは絵本をたくさん読むといいですよ。文字の多さは気にしなくても大丈夫。
うちの子も小学生になったばかりのときには、まだ絵本ばかりを読んでいて、字の多い本を嫌っていたんです。
「このままで大丈夫かな?」と心配になったときもあったんですね。
少しずつ、今回の記事のような方法で、子どもの好きそうな本にたくさん触れさせていったところ、今では進んで単行本の子ども文庫の本も読むようになっています。
本や物語を読むことが楽しいと感じているんですよね。
あくまでも本が嫌いな子には無理に読ませるのではなく、楽しませることがポイントだということをお忘れなく!
本に触れる時間を定期的につくって、本の楽しさに気づくことができればどんなに本が嫌いな子も、好きになってくれますよ。

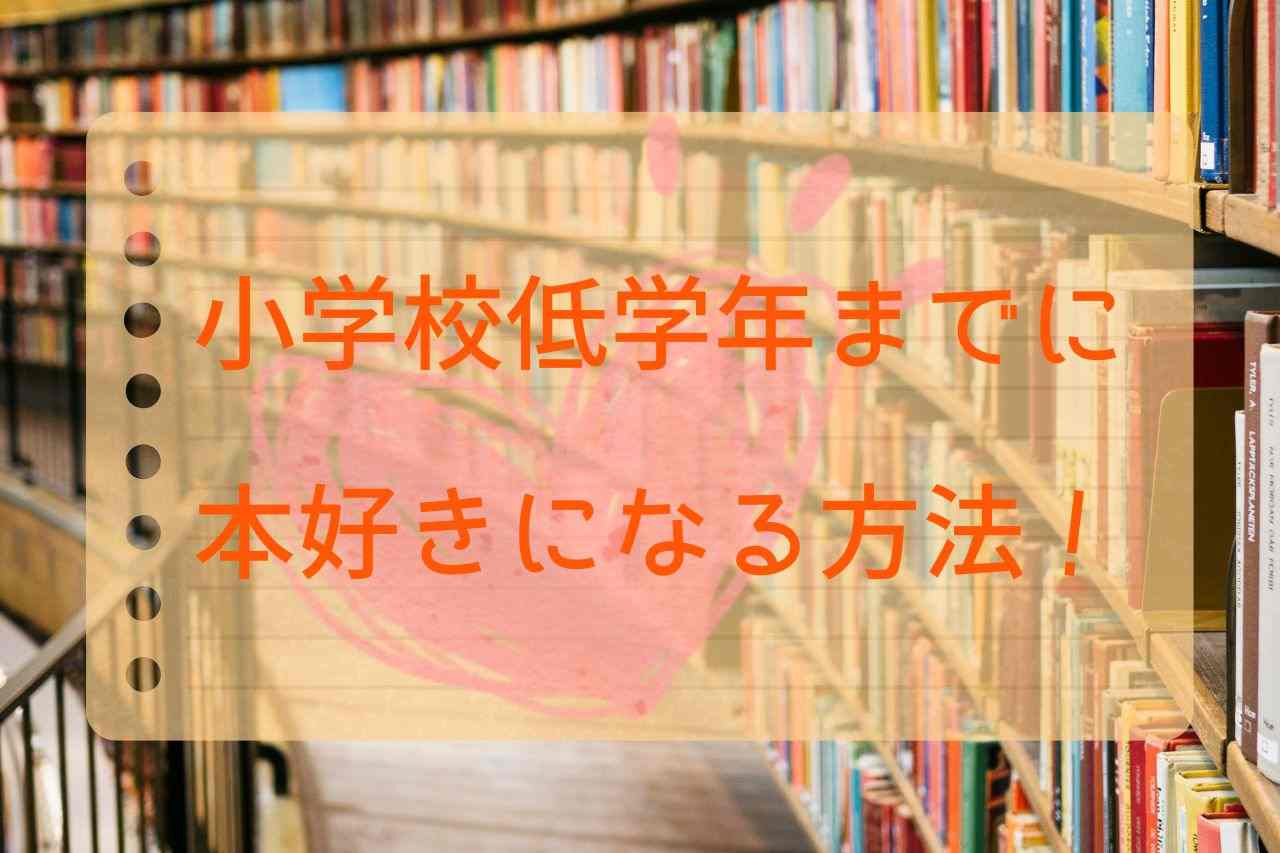
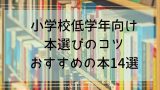


コメント